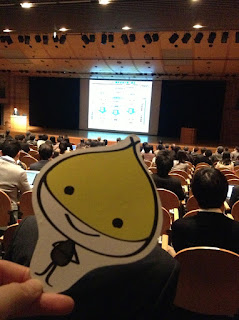会議をビジュアル化することのメリットについて、前回のブログでご紹介しました。
今回は、仕事をしていく中で、どのような場面で活用できるのかについて触れていきます。
今回は、仕事をしていく中で、どのような場面で活用できるのかについて触れていきます。
思考を助け、深める、ビジュアライズの役割
1. ブレストで、イメージを掻き立てる
アイディアを出しあう会議、ブレインストーミングでもビジュアライズは活用できます。例えば、未熟なアイデアを1枚の絵に描きだすこともその一つ。
未熟なアイデア、すなわち「よくわからない意見」は、共感もされなければ、すぐに忘れられてしまいます。しかし、絵に描かれることで、なんとなくわかる状態になり、アイデアとして形をもって存在することができるのです。
また、絵は多義的でもあります。人によって見たものから違う意味を見出し、新しいアイデアを思いつくことも。見る人の多くにイマジネーションを与え、共感してもらうことができます。
2. ディスカッションで、意見を構造化する
ディスカッションの会議でも、ビジュアライズは有効です。例えば、参加メンバー全員の意見を1枚のボードに構造的に整理することもその一つ。
通常、ディスカッションの議事録は、個人個人がメモとして記述することが多いのではないでしょうか。しかし、意見を全員で共有できるように可視化することで、参加者全員が会議の進捗状況を俯瞰して把握できるようになります。
また、記述方法についても、意見の“内容”で構造化するようにするだけで、内容にフォーカスした建設的な話し合いに発展します。「違う視点で発言してみよう」という意識を目覚めさせることも。
3. 意見交換の場で、個々の主張を一覧にする
大きな紙に、スピーカーの特徴と発言背景と主張内容をひと目でわかるように表現します。このようなビジュアルレポートがあれば、耳で聴いていた内容を、見た目で再確認することができ、聴講者は理解を深めることができます。さらに、記録者の解釈を聴講者が再確認することで、人によって異なる解釈に気づいたり、異なる解釈からあたらしい知見を得ることが可能となります。
※ここで紹介した3つのケースは、どれも、記録者の解釈が介入することが許されるケースである。
(議論の内容が解釈できる程度の知識があることが前提ではあるが)記述の正確性よりも、
記述することによって新しい発見をもたらし、議論がおき、場が活性化することを目的としている。
クリエイティビティを高めるビジュアライズの役割
1. コミュニケーションを促進し、アイデアを磨き上げる
上記で挙げた3つケースのように、ビジュアル化された意見、アイデアは、より多くの人に伝わり咀嚼されやすくなる特徴があります。多くの人に伝わり再咀嚼されることで、新しい意味が付加され、切磋され、磨かれる。結果的に、早い段階でビジュアライズされたアイデアは質の高いものになりやすくなります。
2. 想いを探り、強固にする
また、見えないものを見えるようにできるという点で、ビジュアライズは、人の「想い」を形にすることが可能です。
新しいサービスのコンセプトをつくる場合、作る人本人の想いを明確にすることが求められます。それは、顧客のニーズを探ってだけいてもわからない。
「なんのために作るのか?」ものづくりの原点ともなるこの問いに応えるには、客観的に書き出し、構造化し、人の意見と照らしあわせて、理解する、ビジュアライズが効果的です。